モデルチェンジしたBX

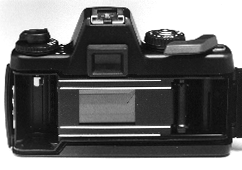
フォトキナ'88では、Bシリーズ初のフルモデルチェンジとして、プラクチカBX20とBX10が登場した。BX20が絞り優先AEとマニュアル両用機、BX10が絞り優先AE専用機でDXコード対応である。プラクチカBX20の最大の改良点は、フラッシュがTTL調光になったことだ。TTLフラッシュ用の受光素子はミラーポックス底面中央にレンズ側へ向けて理込まれ、フィルム面の反射光を小さな凹面鏡を経て測光するユニークな方式になっている。
ホットシューの連動接点はオリンパスOM-2NやOM-4等と同一で、フラッシュが共用可能である。オリンパスの場合は、シャッター速度をマニュアルにするとフラッシュのTTL調光ができなくなるが、プラクチカでは1/125秒以下の全速度でフラッシュのTTL調光が可能である。シャッターダイヤルのX接点用矢印マークは1/100秒となり、機械式制御ではなくなった。
ファインダー内にはAEロックと露出補正警告のLED表示、シャッターチャージ前は絞り表示窓が赤くなる巻上警告が追加された。
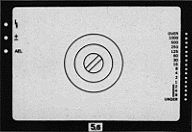 レリーズボタンは大型のシャッター速度ダイヤルと同軸化、ダイヤル前面にレリーズロックリングを設けている。レリーズポタンを押す指先がシャッターダイヤルに邪魔されがちなBシリーズと比べ、周囲に余裕ができスムーズに押せるようになった反面、ストロークが長めになった。レリーズの歯切れの良さは従来型が優れている。また、シャッターショックは多少改善された反面、レリーズ時に必ずAEロックランプが点灯する方式になり、実際にシャッターが作動するまでのタイムラグも長くなった。従来型はきわめて反応が良かっただけに惜しまれる点だ。
レリーズボタンは大型のシャッター速度ダイヤルと同軸化、ダイヤル前面にレリーズロックリングを設けている。レリーズポタンを押す指先がシャッターダイヤルに邪魔されがちなBシリーズと比べ、周囲に余裕ができスムーズに押せるようになった反面、ストロークが長めになった。レリーズの歯切れの良さは従来型が優れている。また、シャッターショックは多少改善された反面、レリーズ時に必ずAEロックランプが点灯する方式になり、実際にシャッターが作動するまでのタイムラグも長くなった。従来型はきわめて反応が良かっただけに惜しまれる点だ。
ポデーサイズはわずかに大きくなり、ボデーの右側が長い一般的スタイルとなった。内部機構は全面的に改められ、凝ったメカニズムのクイックリターンシャッターが廃され、日本のコパルスクエアと良く似た先・後羽根とも4枚となり、測光方式はファインダー内光路による平均測光に近いものとなった。このためペンタ部がやや高くなった。ミラーポックスが広げられ、反射防止塗装がより光吸収性の良いものになるなど、内面反射対策も向上している。
このほかの変更点としては、巻戻しボタンが上面に移動し、シャッターダイヤルの指標を兼ねるようになった。従来は実質8秒前後だったセルフタイマーの作動時間が、10秒までに延長。エプロン右側のレバーを押上げる方式だったプレビュー装置は、セルフタイマーレバーを兼ねたものになり、レンズ側に倒すと絞り込む方式に変更された。AEロックボタンは左前面に移され大型化した。シンクロはホットシュー専用となり、エプロン左のPCソケットは廃された。
ポデー外装は裏蓋を除いて全面的にプラスチック化された。コストダウンのためか、ポデー全体が梨地の無塗装のままであり、上下カバーとエプロンの接合部がスムーズさに欠けるなど、やや高級感に欠ける仕上がりとなった。
その後、BX20をDXコード対応としたBX21も登場した。なお、プラクチカBXシリーズは、発売元の表記が従来のペンタコンから、カールツァイス・イエナに変わっているものもある。ブランド力をアピールする市場戦略によるものか、あるいは社会主義末期の企業合同によるものか、ほんとうの理由は不明である。